
丸山幹治は『副島種臣伯』において、副島の『精神教育』から抜き書きしている。前回に続き、第五編以降を見ていく。
〈第五編は「良知」である。「人の念々の動くのは多くは皆慣習であるものだから、忠孝の習慣の厚いものは常にその念が動き、又忠孝といふ者を常に思はぬものは其の念は決して動かぬ、そこが習相違である」「中庸に天命之謂性、率性之謂道(天の命ずるをこれ性と謂い、性に率うをこれ道と謂い)とある、率性とは即性のまゝといふことである、性のまゝなるが道なれば、道と性とは同一なるもので、差つたものでないといふことが分るであらう」「中庸にも君臣也。父子也、夫婦也、昆弟也、朋友之交也、五者天下之達道也とある通り畢竟五倫といふものより外に道といふものはない筈のものである」「伊邪那岐、伊邪那美の二柱の神が生れましたといふは、夫婦の義であらう、其れからだん〲と多くの神々が生れましたといふは、即、父子の義であらう、葦原千五百秋之瑞穂国是我子孫可王之地、宜爾皇孫就而治焉とあるは君の義であらう、臣下よりいふときには、臣の道が其れから生ずるものであるから、やはり君臣の意味である、庸佐夜芸互阿理祁理といふ場合からだん〲と万民が相輯睦するといふのは、即、朋友の交がそれから教へらるゝのである、それから先づ兄なる皇子より即位に即かせられて、次に弟の皇子に及ぶといふのが経である。間々その時によつて弟が先立たれたこともあるけれども、それは権である。これから長幼の道も明になつて居る、かやうに五倫の道といふものは決して支那から教へられたのでなく、自然に備てゐる」「すべて君父には不較といふて、何であらうが是非曲直を較ぶるといふことをせぬが、臣子たる者の道である」「道といふ字は首に辵すなはち首が走ると書てある、即、頂に来住める神が走るの意味であらう」「貴といふ字は一中が貝(タカラ)なりと書てある」「一文字を作つた蒼頡といふ男はなか〱えらいものであつた」など〉
月別アーカイブ: 2020年4月
副島種臣『精神教育』②
丸山幹治は『副島種臣伯』において、副島の『精神教育』から抜き書きしている。前回に続き、第三編以降を見ていく。
〈第三編「日本の教育」には「日本の教育といふは他ではない、老人も小児も、男も女も、皆ひとしく吾等は先祖代々、万世一系の天皇さまの下に居るものであれば、この一系の天皇さまの御為には、何時でも身命を擲て御奉公申上げるといふの心を養ふことである」「この大なるものが立てば、其余の小なるものは随て立つのである」「兵隊が平日は日本帝国万歳といつて空に教へられて居るのが、愈々戦争の時になつて遼東とか旅順とかにて絶叫する時は 天皇陛下万歳と言つて帝国万歳とは言はぬ、そこが自然と一天万上の君を戴きて居る所を顕はしたといふものである」「不得已といふことはどうしてあるものだ、不得已といふことの証拠は荒魂である、已に荒魂則勇の魂を享けて居る以上は、我に敵するものに打勝たなければならぬ」「養ふべきは大勇である、爾後に大仁を天に施し得るのである」などなどある。
第四編は「道徳」である。「孔子の書に道徳と二字接続してこれを言ふものあるを見ず而して接続して之をいへるは史記の老荘申韓伝に出でたり」「孔子の書に単に道と云ひ徳と言ふも、皆善道善徳を称する者にして決して悪道悪徳を称するものに非ず」「孔子の道を論ずるや夫婦の愚可知矣といへり、失婦の愚、豈天下の達道、天下の達徳なる者を逃れ得んや、老子が云ふ如き空言無実なるものゝ比すべきに非ず、徳をノリとす、即ち乗り行ふべき者の謂なり。出言為度の度なり、乗も同義なり」などなどある〉
副島種臣『精神教育』①
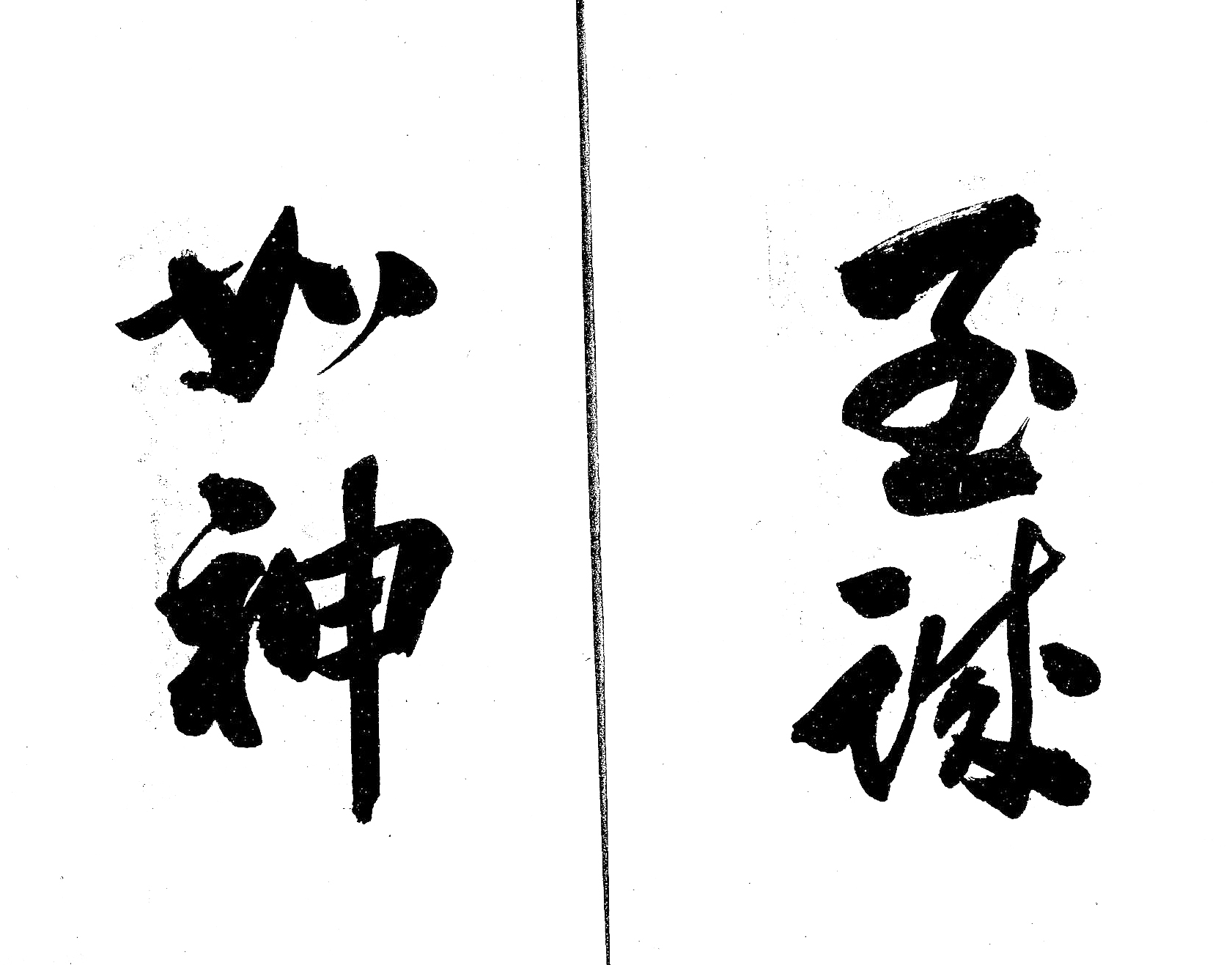
丸山幹治の『副島種臣伯』に「先生の日本主義」という一節がある。
これは、副島の『精神教育』から丸山が抜き書きしたものである。『精神教育』は副島の門人、川崎又次郎が編纂し、同佐々木哲太郎が校閲した。
〈第一編「教導」には、「教ふる時は半分は自分の学問するといふ心あひで教へねばならぬ」「師たるものは言々語々言葉に注意していはねばならぬ」「人を教ふゆるには愛を表にしてゆかなければならぬ。智の方は以心伝心でゆくがよいものである」「孔子の出門如見大賓といふのは、一口にいはゞ人を慢らぬといふまでゞある、人を呵る時は此者の顔にも神は宿つてござると思ふ所である」「凡天下に志あるものは何時で靄然として仁天下を蓋ふものがあるによつて、天地と度を合するものである」。などなどある。
第二編「感化」には「彼の楠氏の時代には、武蔵相模の兵は、日本中寄つても之に当る者が無いといふ程強かつたが、五畿内の兵は、鞭で打たれても直ぐに斃れるといふ程弱い者として有つた、然るに其の鞭で打つても斃れる弱い五百人の兵士を楠が率ゐると、楠の義勇の精神は、直に五百人の兵士の心となり、日本中の兵を引受けて宜いといふ武蔵相模の兵と戦ふて、彼は散々逃げても、楠の兵は一人も逃げたといふ事はない」「楠、児島の精神を知るに依つて万劫末代、志士仁人を起して行く、足利尊氏の為めに奮ひ起つたといふものは一人も無い」「智慧と智慧で来る時は互に相欺くばかりである」「楠の死んだ時でも其首を賊兵が楠の郷里に送つて遣つたと云ふ様な伝へがあるものである、賤までが感ずる」「高山彦九郎の日記と云ふものがある、信濃の人で林康之といふが其日記を持つて来て見せられた事がある。粗末な紙に書いてある、其に高山が伏見を通つた時、伏見に戦気が見える、他日事の有るならば、伏見から始まらうと言つた事が書いてある、然るに御維新の際、伏見の戦争が第一着であつた」「感応とか、感招とか、感化とか、自然と天地人相通ずる所の者がある」「感招の理は信長が一人、尾張に起ると秀吉とか蒲生とか誰とか言ふ様な有名な人は悉く尾張から起つた、家康一人三河から起ると、天下を定むるに足る伎倆の輦が矢張三河から起つた」「富士山も平にすれば何にもならぬ。横幅を利かさぬから高くなる」「孔子等は其人の長ずる所に依つて、一方に長じた人に、一方を長じさする、何もかも利かすと平くなつて何処も利かぬ様になる」などなどある〉
「王命に依って催さるる事」─田中惣五郎『綜合明治維新史 第二巻』
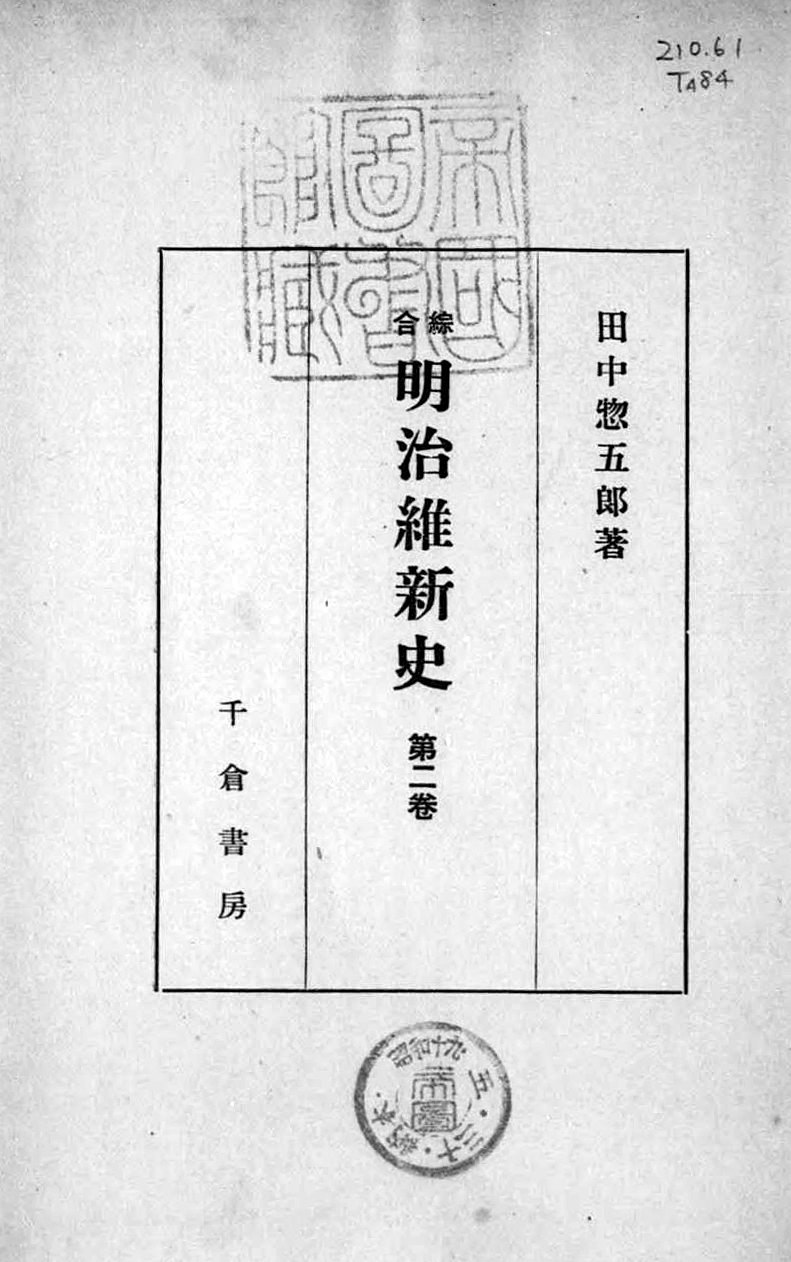
田中惣五郎は『綜合明治維新史 第二巻』(千倉書房、昭和十九年)において次のように書いている。
〈尾州藩主義直の尊王心は著名であり、大義名分に明かであるとされて居るが、水戸義公の大日本史編纂もこの叔父義直の啓発によるところ尠しとしないと言はれて居る。従来この藩のことは閑却され勝であつたから少しく筆を加へて置かう。義直の著「軍書合艦」の巻未には「依王命被催事」といふ一筒条があつて、一旦緩急の際は尊王の師を興す意であつたと伝へられる。しかしこれは恐らく群雄の興起した際のことであつて、本家の浮沈に当つては、水戸同様いづれにも与せぬ方針と解すべきであらう。そしてこの事は文書に明確にすることを憚り、子孫相続の際、口伝に依て之を伝へた。そして四代の藩主吉通が二十四歳で世を去り、其の子五郎太が尚幼少であつたから、忠臣で事理に通じた近臣近松茂矩に命じて成長の後に伝へしめたものが、所謂「円覚院様御伝十五条」の一で、御家馴といはれるものである〉
政府の覇道主義的傾向を戒めた石原莞爾─「東亜連盟建設要綱」

明治期のわが国においては、興亜論、アジア主義が台頭した。アジア諸民族が連携して欧米列強の侵略に抵抗しようという主張であり、欧米の植民地支配を覇道として批判するものだった。しかし、国家の独立を維持するためにわが国は富国強兵を推進し、列強に伍していかねばならなかった。その結果、日本政府の外交は覇道的傾向を帯びざるを得なかった。
そのことを在野の興亜論者たちは理解していた。ところが、やがて在野の興亜論者たちも政府の政策への追随を余儀なくされていく。こうした中で、その思想を維持した興亜論者もいた。例えば石原莞爾である。彼が率いた興亜連盟は、戦時下にあってもその主張を貫いていた。大東亜戦争勃発後に改定された「東亜連盟建設要綱」は以下のように述べている。
〈明治維新以来、他民族を蔑視し、特に日露戦争以後は、急激に高まれる欧米の対日圧迫に対抗するため、日本は已むなく東亜諸民族に対して西洋流の覇道主義的傾向に走らざるを得なかった結果、他の諸民族に対する相互の感情に阻隔を来したのは、躍進のための行き過ぎであり、日本民族の性格からいえば極めて不自然のことである。日本民族が、国体の本義に覚醒し、かつ国家連合に入りつつある時代の大勢を了察するならば直ちにその本性に復帰すべく、東亜諸民族の誤解を一掃することは、極めて容易であると信ずる。そうなれば一つの宣伝を用いることなく、東亜諸民族が歓喜して天皇を盟主と仰ぎ奉ること、あたかも水の低きに流れるが如くであろう。
しかし、遺憾ながら東亜諸民族が心より天皇を仰慕することなお未だしとすべき今日、日本は東亜大同を実現する過程に於て、聖慮を奉じて指導的役割を果す地位に立つべき責務を有する。ただしこの指導的地位は、日本が欧米覇道主義の暴力に対し東亜を防衛する実力を持ち、しかも謙譲にして自ら最大の犠牲を甘受する、即ち徳と力とを兼ね備える自然の結果であらねばならぬ。権力をもって自ら指導国と称するは皇道に反する。(中略)
今や大東亜戦争遂行過程にあり、我が国民が急速に英米依存を清算して、肇国の大精神に立帰りつつあることは、誠に喜ぶべきところであるが、ややもすれば時勢の波に乗じて、軽薄極まる独善的日本主義を高唱するものが少なくない。
天皇の大理想を宣伝せんとする心情やよし。しかれども日本自らが覇道主義思想の残滓を清算する能わず、外地に於ては特に他民族より顰蹙せられるもの多き今日、徒に「皇道宣布」の声のみを大にするは、各民族をして皇道もまた一つの侵略主義なりと誤解せしめるに至ることを深く反省すべきである。「皇道宣布」の宣伝は「皇道の実践」に先行すべきでない。〉
康有為─もう一つの日中提携論

日清両国の君主の握手
「抑も康有為の光緒皇帝を輔弼して変法自強の大策を建つるや我日本の志士にして之れに満腔の同情を傾け此事業の成就を祈るもの少なからず、此等大策士の間には当時日本の明治天皇陛下九州御巡幸中なりしを幸ひ一方気脈を康有為に通じ光緒皇帝を促し遠く海を航して日本に行幸を請ひ奉り茲に日清両国の君主九州薩南の一角に於て固く其手を握り共に心を以て相許す所あらせ給はんには東亜大局の平和期して待つべきのみてふ計画あり、此議大に熟しつつありき、此大計画には清国には康有為始め其一味の人々日本にては時の伯爵大隈重信及び子爵品川弥二郎を始め義に勇める無名の志士之に参加するもの亦少からざりしなり、惜むべし乾坤一擲の快挙一朝にして画餅となる真に千載の恨事なり」
これは、明治三一(一八九八)年前後に盛り上がった日清連携論について、大隈重信の対中政策顧問の立場にあった青柳篤恒が、『極東外交史概観』において回想した一文である。永井算巳氏は、この青柳の回想から、日清志士の尋常ならざる交渉経緯が推測されると評価している。両国の志士たちは、日本は天皇を中心として、中国は皇帝を中心として、ともに君民同治の理想を求め、ともに手を携えて列強の東亜進出に対抗するというビジョンを描いていたのではあるまいか。
変法自強運動を主導した康有為は、一八五八年三月に広東省南海県で生まれた。幼くして、数百首の唐詩を暗誦するほど記憶力が良かったという。六歳にして、『大学』、『中庸』、『論語』、『朱注孝経』などを教えられた。一八七六年、一九歳のとき、郷里の大儒・朱九江(次琦)の礼山草堂に入門している。漢学派(実証主義的な考証学)の非政治性・非実践性に不満を感じていた朱九江は、孔子の真の姿に立ち返るべきだと唱えていた1。後に、康有為はこの朱九江の立場について、「漢宋の門戸を掃去して宗を孔子に記す」、「漢を舎て宋を釈て、孔子に源本し」と評している。 続きを読む 康有為─もう一つの日中提携論