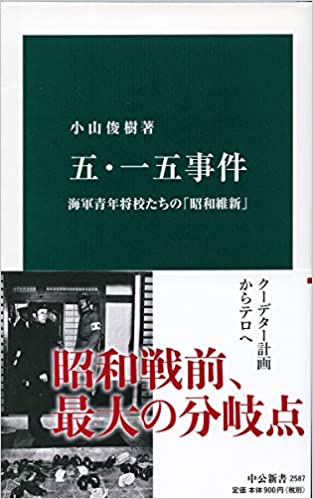第一部 高須藩ゆかりの地をめぐる─尾張藩尊皇思想の継承者
水戸義公と極めて近い関係にあり、水戸・尾張両藩の尊皇思想継承において特別な役割を演じたのが、高須藩祖・松平義行です。高須藩は、幕末の高須四兄弟でも知られています。10代藩主・松平義建の次男:慶勝(尾張藩14代藩主)、五男:茂徳(尾張藩15代藩主)、七男・容保(会津藩主・京都守護職)、八男・定敬(桑名藩主・京都所司代)の四兄弟です。四兄弟生誕の地とされるのが、金丸稲荷神社です。
高須藩の江戸屋敷が置かれた新宿区荒木町一帯には、その歴史が今もとどめられています。津の守弁財天の境内には、屋敷を偲ぶ小さな池亭があります。津の守と名付けられたのは、義行以来、高須松平家は代々「摂津守」を称していたからです。四谷2丁目付近の新宿通りから、曙橋付近の靖国通りまでを南北に結ぶ通りは、「津の守坂通り」と呼ばれています。

付近にある新宿歴史博物館では、平成26年に「高須四兄弟 新宿・荒木町に生まれた幕末維新」と題した特別展が開催されています。ちなみに現在、特別展「生誕170年記念 小泉八雲」を開催中(12月6日まで)。
今回は、『柳子新論』の著者で明和事件で死罪に処せられた山県大弐先生のお墓がある全勝寺(新宿区舟町11-6)も訪れます。さらに、四谷十八ヵ町の総鎮守、須賀神社にもお参りします。
第二部 『靖献遺言』を読む会
『靖献遺言』は、山崎闇斎先生の高弟である浅見絅斎先生(1652年~1712年)の主著ともいうべき作品であり、崎門学の必読書です。本書は、貞享4(1687)年、絅斎先生が35歳の時に上梓し、君臣の大義を貫いて国家に身を殉じた屈平、諸葛亮、陶潜、顔真卿、文天祥、謝枋得、劉因、方孝孺等、8人の忠臣義士の略伝と遺言を編纂しています。絅斎先生は、本書に登場する8人の忠臣義士に仮託して君臣内外の名分を正し、尊皇の大義を説きましたが、こうした性格を持つ本書は、その後、王政復古を目指す尊皇討幕運動のバイブルとして志士たちの間で愛読されました。なかでも、橋本左内などは、常時この『靖献遺言』を懐中に忍ばせていたと言われ、尊攘派志士の領袖として討幕の端を開いた梅田雲浜は、交際のあった吉田松陰から「『靖献遺言』で固めた男」とも評されました。かく評した松陰自身も野山獄でこの書を読み感銘を受けています。
昨年は崎門学の学祖、山崎闇斎先生の生誕400年を迎え、崎門学の必読文献である『靖献遺言』への注目が高まっています。そこで弊会では、月例の勉強会として、以下の要領で『靖献遺言』を読む会を開催し、崎門学への理解を深めると共に、絅斎先生が本書に仮託した尊皇斥覇の現代的意味について考えたいと思います。
つきましては、多くのご参加をお待ち申し上げております。
記
第一部 高須藩ゆかりの地をめぐる
日時 令和2年12月6日(日)13時集合
集合場所 全勝寺(新宿区舟町11-6、四谷三丁目駅から徒歩5分)
コース ①全勝寺→②津の守弁財天→③金丸稲荷神社→④新宿歴史博物館→⑤須賀神社
第二部 『靖献遺言』を読む会
時間 16時~18時
場所 新宿区四谷1丁目7-9 ホテルニューショーヘイ2階
テキスト 『靖献遺言』(講談社学術文庫)。各自ご持参下さい。
連絡先 (tsubouchi@ishintokoua.com、090-5788-3851)
わが国の伝統医学「和方」の復興を試みた人物として、権田直助に次いで挙げられるのが本居宣長である。宣長は『鈴屋答問録』で次のように述べている。

「何れの病も、神の御しわざにあらざるはなし。さて病ある時に、或は薬を服し、或はくさ〲のわざをして、これを治むるも、又皆神の御しわざ也。此薬をもて、此病をいやすべく、このわざをして、此わづらひを治むべく、神の定めおき給ひて、其神のみたまによりて、病は治まる也」
この宣長の記述について、菅田正昭氏は〈これはまさしく皇朝医道としての〈和方〉の考え方である。そうした観点に立てば、宣長の有名な二首「たなつ物もゝの本草も天てらす日の大神のめぐみえてこそ」「朝よひに物くふごとに豊宇気の神のめぐみをおもへよのひと」も、単に食物への感謝を歌ったものではなく、無上至極の尊き宝としての食物をしっかり噛んで食べれば、その人の身体と霊魂の中に伊勢内宮の天照大神と外宮の豊受大神が顕現する、という霊的食養道としての〈和方〉の極意を詠んだものであることがわかる〉と指摘している。
栗山潜鋒の『保建大記』を読了した。潜鋒は山崎闇斎の高弟である鵜飼錬斎と桑名松雲に師事し、第百十一代後西天皇の皇子である八條宮尚仁親王の学友として近侍した。潜鋒が親王に近侍したのは14歳の時であり、両者は同年齢であった。以来、潜鋒は、親王に錬斎、松雲から受け継いだ闇斎の学を伝え、彼が元禄元年、18歳のときに親王に献上した書が『保平反正録』である。その後、この書名に含まれる「反正」は反正天皇の諡号であるため、書名を『保平綱史』と改めた。何れにしても「保平」とあるのは保元平治の両兵乱のことである。
ところが、本書を献上した翌年、親王は俄かに早世し給い、潜鋒は悲歎に暮れたが、彼の卓越した学識を認めた水戸光圀は、『大日本史』編纂の史局である彰考館に彼を登用し、かくして潜鋒は光圀に仕えることになった。この水戸出仕中に、彼が先輩同僚との議論を経る中で前出の『保平綱史』に大幅な改訂を加えたのが『保建大記』である。今度の書名が「保平」ではなく「保建」となったのは、潜鋒が朝威失墜の根本原因を、保元平治の兵乱による武家の簒奪ではなく、むしろそれを出来した朝廷内部、なかんづく後白河天皇の失徳に求め、平治とこの天皇が崩御し給うた建久の年号を以って書名に冠したからである。
近藤先生によると、潜鋒が光圀に仕えた意義は重大である。というのも、『大日本史』は、光圀の意向によって、以下の三大特筆を有するとされる。すなわち第一に、神功皇后を帝紀より除いて后妃伝に入れること。第二に、大友皇子を帝紀に入れること、そして第三に南朝を正統とすることである。しかしその内第三の点は、今上天皇が北朝の御血筋であることから彰考館の内部でも反対意見が強かった。その際、潜鋒が水戸での出仕中に到達した独自の神器論は、『保建大記』のなかに盛り込まれ、光圀の素志を道義と史実の両面において論証したのである。
ここでいう潜鋒の神器論は「躬に三器を擁するを以て正と為すべし」というをその眼目としていた。これに対して、彼の同僚である三宅観瀾は『保建大記』に寄せた序文において「神器の存否を以てして、人臣の後背を卜する者とは、議竟に合はず」と記し、皇位にとって重要なのは神器ではなくて天皇の君徳であると反論したが、この考えは、同書の跋文を書いた安積澹泊といった彰考館の他の同僚についても同様であった。

近藤先生のいわく、「思うに土地といひ家屋といひ、その所有を主張するものが複数であって互ひに所有の権利を争ふ時には、その土地や家屋の権利書を所持してゐるものを正しい所有者と判断せざるを得ない。されば人はみな権利書を大事にして失はぬやう盗まれぬやう、だまし取られぬやう、その保管に心を用ひるのである。神器もその性格、ある意味では権利書に似てをり、皇統分立していづれが正しい天子であるか知りがたく、人々帰趨に苦しむ時は、神器を有してをられる御方を真天子としてこの御方に忠節を尽くさねばならない。いはんや神器は権利書と異なり、その由緒からいへば大神が天孫に皇位の御印として賜与せられし神宝であり、大神の神霊の宿らるるところとして歴代天皇が奉守継承して来られた宝器であり、極言すれば、天祖・神器・今上の三者は一体にして、神器を奉持せられるところ、そこに天祖がましますのである。」(近藤啓吾先生『続々山崎闇斎の研究』所収「三種神器説の展開―後継者栗山潜鋒」)
続きを読む 折本龍則「『保建大記』における神器論の問題」(『崎門学報』第2号、平成27年1月1日) →
帝京大学の小山俊樹教授が、『五・一五事件 海軍青年将校たちの「昭和維新」』(中公新書)で、第42回サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を見事に受賞された。
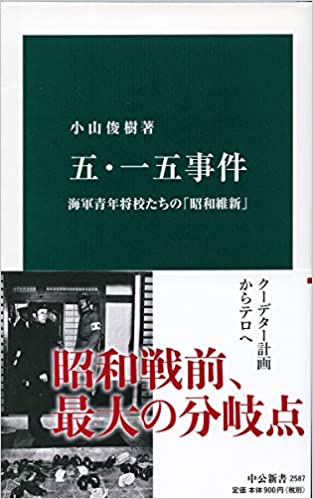
『大亜細亜』は、平成29年に小山教授が上梓された前作『評伝 森恪 日中対立の焦点』(ウェッジ)に関して、インタビューをさせていただいた(インタビュー・構成 小野耕資)。そこで「一九二〇~三〇年代に起きたことは、世代を超えて語り継がれていきます。とくにほとんどが刑死した二・二六事件と異なり、五・一五事件の主要な関係者は、戦中戦後も生きています。彼らにとって戦後とはどういう時代だったか。このことを考えながら、五・一五事件を描ければと思っています」と述べられていたことが印象深い。
以下、『大亜細亜』第6号(平成30年7月)に掲載した小山教授のインタビュー記事「西洋列強との協調と相克の近現代史」全文を紹介します。
帝京大学文学部史学科教授の小山俊樹先生は日本近現代史専攻で、昨年(平成二十九年)、『評伝 森恪 日中対立の焦点』を上梓された。森恪は戦前日本の大陸政策に関与した人物で、小山教授は森とアジア主義者との関わりにも言及している。そこで同書の内容を中心に、戦前のアジア主義運動史について、平成三十年六月六日にインタビューを行った。

―─ 森恪に興味を持ったきっかけは、どういったものでしたか。
博士論文(『憲政常道と政党政治 戦前二大政党制の構想と挫折』)を執筆した際に、二大政党時代の政党政治研究がまだまだ薄いと感じました。そして論文では、森恪が当時の政界のキーマンとして度々登場するので、いずれは本腰を入れてまとめなければと考えていました。そこに、ウエッジ社編集部から中国関係の人物伝を依頼されたので、それではと挑戦することにした訳です。
一般には森の知名度も高くはなく、編集部にも意外な人選だったようです。森の本格的研究は乏しく、一般には松本清張などの影響で、大陸侵略の陰謀を練った怪しい人物というイメージが先行している状況でしょうか。また、四十九歳という短命で亡くなりますが、その劇的で濃密な生涯に、興味を持ったことも理由の一つです。
続きを読む 小山俊樹教授インタビュー「西洋列強との協調と相克の近現代史」(『大亜細亜』第6号、平成30年7月) →
令和元年11月30日に京都下御霊神社で挙行された山崎闇斎先生生誕四百年祭に、崎門学研究会代表の折本龍則らが参列しました。

まず午後1時過ぎから垂加霊社で出雲路宮司による神事が営まれ、その後国学院大学の西岡和彦教授が「闇斎先生と中臣祓」と題して講演されました。西岡氏によると、中臣祓は、闇斎先生が帰幽された際に門人たちが唱えたとされ、君臣合体守中の道を表しております。天孫瓊瓊杵尊が雲の上である高天原から地上に降臨したとするのは本居宣長以来の国学的影響であり、垂加神道では、高天原とは皇居のことであり、天孫降臨とは日向への西遷を意味します。このことは藝林特別号における氏の論文で詳述されています。
講演の後、皇學館大学の松本丘先生が、自ら作成された垂加神道系譜について解説されました。最後に、社務所横の建物で記念展示を拝観致しました。
沖繩を訪ねたのはもう六年も前の話だ。首里城については那覇空港に着いた後、ゆいレールに乘つて眞つ先に足を運んだ場所である。本州から滅多に出る機會のなかつた自分にとつて、まるで海外にでも出向いてゐるやうな昂揚感があつた。
首里驛から城のある首里城公園までは、最寄り驛と云ふにはそれなりに距離がある。しかし二十分近く歩いた末に、遠方から見渡せる城郭の遠望は壯觀である。
そこからまた暫く城内を散策すると、二千圓札でお馴染みの守禮門が迎へてくれる。その創建は明確ではないが、中國がまだ明の時代だつた十六世紀半ばの第四代の尚清王の時代には既に存在してゐたとされる。
當初は「待賢門」とよばれ、「首里」の額が掲げられてゐた。その後、第六代尚永王の時代に明から册封使が派遣される際には「守禮之邦」の額が掲げられるやうになるが、十七世紀半ばの第十代の尚質王の時代にそれが常掲となり、現在の「守禮門」として定着するやうになつたといふ。沖繩戰の首里城燒失後、昭和三十三年に眞つ先に再建されたのが、この守禮門だつた。以來、沖繩觀光の象徴的存在となつた。
そこから城壁を拔け、首里城正殿に向かふわけだが、國内で目にすることができる通常の城郭建築とは大きく異なるその壯大な姿から、映畫『ラストエンペラー』で大冩しにされた紫禁城を想ひ起こす人も少なくあるまい。しかしながら、實際はその中心部には、唐破風とよばれる日本の城郭建築特有の意匠が施され、この正殿だけでも東アジアの傳統建築の樣々な要素がふんだんに織り込まれてゐることに氣づく。
廣場の南殿は主に薩摩の使節を受け容れ、疉敷きの和風樣式となつてゐる。一見、大陸風の外観に、日本國民にとつて馴染み深い畳敷きの部屋があるのには、何とも親近感を覺えずにはゐられない。一方、明朝以來、清國とも外交儀礼上、朝貢關係を結んでをり、册封使を迎へ入れる北殿は、南殿とはおよそ対照的な中華風の建物となつてゐる。
正殿内部は博物館となつてをり、元は「京の内」とよばれる古神道の樣な祈祷場の他、政治外交を司る「表」、更には江戸城大奧のやうな「御内原」とよばれる施設もあつた。中世から近世の城郭建築のみならず、京都御所で云へば政廳の場だつた紫宸殿、日常生活の間の清涼殿を併せ持つ施設でもあつたやうだ。 続きを読む 山本直人「首里城の夢の跡」(『維新と興亜』第2号) →
国家と社会の反目
前号では、明治草創期において矛盾なく調和していた「国家」と「社会」が次第に乖離をきたし、従来の国家主義運動が行き詰まりに直面したなかで、津久井龍雄によるような、新たな国家主義運動が出てきたことを述べた。すなわち、かつてにおいては、尊皇を蝶番として国権と民権は結びついていたが、やがてマルクス社会主義者によって、国家は資本と結託して人民を搾取抑圧する権力装置と見做され、こうした傾向は、治安維持法で「国体の変革」と「私有財産制度の否認」が結びつけられたことで決定的になった。国家は資本の軍門に降ったのである。
また対外的にも、日露戦争に勝利したころまでは、我が国の国権伸張は、欧米に侵略支配されたアジアの解放と結びついていたが、やがて我が国が大陸での権益を獲得するにつれ、それは欧米帝国主義への追従、アジアの資本主義的近代化の様相を強めていった。かくして国家主義と社会主義は相いれざるものとされ、旧来の国家主義運動は、国家の内外において行き詰まりの様相を呈していた。こうしたなかで、津久井龍雄は、高畠素之の門下として、社会主義インターナショナリズムと、国家と結託した資本主義(現代でいうネオリベラリズム)の双方を排撃し、天皇中心政治の旗印のもとに新しい国家主義を標榜して、国家と社会の総合止揚を図ったのである。
権藤成卿の農本自治主義
こうした津久井の国家社会主義思想との対比で面白いのが権藤成卿の農本自治思想である。権藤は、農本主義の思想家であり、5・15事件など昭和維新運動にも少なからぬ影響を与えた人物である。権藤の思想と人物については、筆者も執筆者の一人に名を連ねた『権藤成卿の君民共治論』(令和元年、展転社)をご参照頂きたい。

権藤は、薩長の有司専制による明治国家体制はプロシア式の官治制度であると批判し、これに対置される理想として、農村を中心とした社稷自治を唱えた。権藤にとって「社稷」とは、農を中心とした国民の衣食住であり、「宗廟」としての国家は、社稷を守るためにあるのであって、その逆ではない。
彼は『君民共治論』で曰く、〈日本は国初以来皇室と国民と共に社稷を尊奉し、自然而治の成俗を保持漸化させ、継体朝に至りさらにこれを具体的に「宗廟を奉じて社稷を危うすることを獲んや」と宣命されたのである。ほんとこれ社稷民人を安泰ならしむるがために、宗廟朝廷を尊奉するのである。それが宗廟朝廷の尊奉は慴服となり、阿附となり、臧官涜吏に屈従して功利を競うようになれば、たちまち社稷民人の生存は危殆に陥いる。当時千秋万歳を叫び続けて国を滅ぼした司馬晋もあれば百済もあった。由来、宗廟朝廷を尊奉するのは、臣民としてもとより当然のことである。しかもその宗廟朝廷の鞏固なる基礎は社稷民人衣食住の安定にある。いわゆる衣食足りて礼節を知るということにあれば、宗廟朝廷の威服のみを拡充して社稷民人を馭御誅圧すれば、その国の根底基礎はたちまちにして決壊する。ゆえに孟子はこれを「社稷を重しとなし、君を軽しとなす」と喝破しておる。この深意は各人の考慮思索をもって会得すべきもので、一々これを引証的に講述することは宜しく慎まねばならぬ。要は我社稷体統の国性をプロシア式国家学説に附会せし官僚学者の謬妄を理解さるれば事自ら分明である。〉
権藤によると、我が国の建国以来の国性は、社稷自治の体統にこそあり、社稷は国家の成立以前から自律的な共同体として成立していた。したがって、国家即ち宗廟は、社稷を補完する制度としての消極的二義的な役割しか認められていない。曰く「凡そ国の統治には、古来二種の方針がある。其一は生民の自治に任せ、王者は唯だ儀範を示して之に善き感化を与うるに留むるのである。其二は一切の事を王者自ら取り仕切って、万機を綜理するのである。前者を自治主義と名づけ得べくんば後者は国家主義と名づけ得べきものなのである。我肇国の趣旨は全く前者の主義によったもので、東洋古代の聖賢の理想は総て此に在った。」
権藤が社稷自治の体統の歴史を記した書に『君民共治』の名を冠したのは、大化二年の詔書に
「それ天地の間に君となり万民を宰る者は独制すべからず。すべからく輔翼を仮るべし。これをもって我皇祖卿等が祖考と共治す。朕また神明の保祐により卿等と共治せむと欲す」(傍点筆者)とあるのに基づき、この詔書に示された大化の改新の理念こそが明治維新の本来的な理想であったにも関わらず、薩長藩閥による明治国家は官治主義的な専制によって社稷自治を破壊し、明治維新の理想から背馳したと権藤は断じるのである。 続きを読む 折本龍則「新しい国家主義の運動を起こそう!②津久井龍雄の権藤成卿批判」(『維新と興亜』第2号) →
シティ・オブ・トウキョー号
シティ・オブ・トウキョー号に乗り込んだ彌平(二十九歳)の傍らには、弟・謹三(十八歳)の姿もあった。謹三は元治元(一八六五)年十月十日生まれ。明治九年(一八七六)六月、東北地方御巡幸中の明治天皇が花巻に立ち寄られた折、里川口金城小学校を代表して天覧授業に出席する栄に浴する〔『花巻市史(近代編)』102~105頁〕など、幼い時から優秀であったようだ。その後、彌平を頼って上京し、明治十五年十二月五日付で兄と同じく慶應義塾に入社した〔『慶應義塾入社帳(第二巻)』537頁〕謹三は、米国への留学を志したのだろう。
シティ・オブ・トウキョー号には、彌平・謹三兄弟のほか、フランス・リヨンに総領事として赴任する藤島正健のほか、大倉喜八郎や濱口梧陵など数名の日本人が乗船していた。
越後国蒲原郡出身の大倉(四十六歳)は、大倉土木組(現・大成建設)、大倉火災海上保険(現・あいおいニッセイ同和損害保険)、日清豆粕製造(現・日清オイリオ)、札幌麦酒(現・サッポロビール)などを創業し、大倉財閥を築き上げたことで知られる。また、自邸の敷地内に大倉商業学校(後に大倉高等商業学校)や大倉集古館を設けた。このうち同校は大東亜戦争における空襲で被災して国分寺に移転し、敗戦後の学制改革で東京経済大学となる。現在、虎ノ門の旧跡地にはホテルオークラが建つ。
彌平との関わりで特筆すべきは濱口(六十四歳)である。紀伊国有田郡出身の濱口は安政南海地震における「稲むらの火」の逸話で知られるが、ヤマサ醤油の前身である濱口儀兵衛家の当主として醤油醸造業を行う事業家、和歌山県会の初代議長を務める政治家としての一面も有する人物だ。
彌平が濱口と同船したのは偶然でなく、示し合わせてのことであった。後年、彌平は次のように振り返っている。

明治十六年私が外国へ行く少し前の事でした。京橋區金六町の自宅に居りますと、福澤先生から御手紙で、直ぐに來て呉れとの事でありましたから、早速お宅へ參上したのであります。先生がお前は今度米國へ行くさうだが、もう定まつたかと云はれるので、決定した旨を申し上げると、それなら相談したい事がある。實は自分の友人の濱口君も米國へ行く計畫をして居るのだがと云つて、種々濱口さんに關する話を聞いたのです。濱口さんの事は此の時初めて聞いたのですが、若い時分の事業、官歴、それから栖原角兵衛を助けた話なども詳しく聞いて、隠れたる偉人だと思ひました。
此の時分濱口さんの渡米するに就て、陸奥宗光も一緒に行かうとの話があつたやうですが、先生は君が行くなら陸奥の方は斷つて君に同行して貰ひたいといふのでした。何でも陸奥さんは私共よりも一船さきに出發された樣に覺えています。
〔杉村『濱口梧陵傳』241頁〕 続きを読む 金子宗徳「金子彌平―興亜の先駆者④」(『維新と興亜』第2号) →
はじめに
日本史年表では、明治七年(一八七四)の「佐賀の乱」。明治九年(一八七六)の「熊本神風連の乱」「萩の乱」「秋月の乱」。明治十年(一八七七)の「西南の役(西南戦争)」の文字を見て取ることができる。これらは、明治新政府に不満を抱く旧士族等の反乱として片付けられる。しかし、不思議なことに、明治四年(一八七一)の「久留米藩難事件」の記述はない。
一般に、この「久留米藩難事件」は長州の大楽源太郎が久留米藩の同志を頼り、その大楽を久留米藩士が殺害した事件と見られる。実際に、大楽が久留米藩に逃げ、殺害されたことが引き金になっているが、当時の状況が詳細に検証された風はない。
そこで、この久留米藩難事件の流れを辿ることで、事件の真相を検証してみたい。そこから、明治新政府が歴史から抹消した真実が浮かび上がるのではと考えている。この「久留米藩難事件」においては、大楽源太郎を殺害した川島澄之介が『久留米藩難記』という
一書を遺しており、これを中心に読み解いていきたい。
もしかして、この「久留米藩難事件」とは、あの真木和泉守の意思を尊重しての、新政府を糺す事件ではなかったかとさえ思える。ゆえに、新政府は、歴史から抹消してしまったのではとさえ、訝りたくなる。
回りくどい話の展開になると思うが、事件の中心人物である川島澄之介の人物像を知るためにも、お付き合いいただきたい。
一、「光の道」
北部九州の神社には、参道が直接、海に繋がっているところが多い。これは、古くから北部九州が外海と結びついていた証拠と考える。福岡県福津市にある宮地嶽神社もその一つだ。その宮地嶽神社では、二月と十月、ダイナミックな「光の道」が出現するが、自然が織りなす雄大な光景に、人々は声を失う。

その宮地嶽神社の日常は、どこにでもある神社仏閣と何ら変わりがない。参道には土産物店が並び、名物の「松ヶ枝餅」(太宰府天満宮の「梅が枝餅」に似ている)を焼く香ばしさに包まれる。ゆるゆると、その石畳を進むと、行く手を阻むかのように石段がそそり立つ。脇には「女坂」と呼ばれる坂道が備わっているが、あえて、「光の道」を体感するために石段を昇ってみたい。 続きを読む 浦辺登「歴史から消された久留米藩難事件」(『維新と興亜』第2号) →
■新型コロナウィルスの拡大が現代に突き付けた課題
新型コロナウィルスの感染拡大が止まらない。本稿執筆時点(令和二年三月二十四日)で一七四か国で三十六万人以上が感染、一万六千人以上の人が亡くなっている。今回の新型コロナウィルスは、現時点ではスペイン風邪やコレラ、ペスト、天然痘など、世界史上繰り返されてきた人口構成が変わってしまうほどの凶悪な致死率には至っていない。しかし全世界に感染が一挙に拡大し、移動自粛ムードにより世界経済全体の後退を招いているという点で、前記の感染症とは異なる事態を招いている。これほどまでに世界中で感染が広まった背景には、ヒト・モノ・カネを自由に行き来することを無条件に肯定してきたグローバリズムの弊害がある。
■グローバリズムの失敗
通信、交通技術の進歩により、市場は国境をはるかに超えて拡大している。だが、そうした中に生まれた「グローバル」な市場には歴史的積み上げがない。グローバル化の結果は惨憺たる失敗に終わっているというべきである。金融関係はリーマン・ショックで破綻し、人材の行き来はあらたな底辺層の登場と、中間層の消失、格差の拡大につながっている。通貨の統合は周辺弱小国の破綻となって跳ね返ってきた。それがなくとも統合により零細農家が続々と廃業しており、失業率は高止まりし、いずれはガタがくる仕組みであった。
いくら言い訳をつけても、自由競争の結果は経済の無政府状態にならざるを得ない。無政府状態という言葉がわかりにくければ、無秩序状態と言い換えてもよい。企業家は雇用や国際競争力を人質にして賃下げの容認を迫る。そのつけは政府が支払わざるを得ない。そうならないように政府は「自由貿易協定」という名の密室の交渉で、自国に有利になるように他国と条約を結ぼうとする。しかし、それが成功したとしても、やはりそのうまみは一%にしか入らず、九十九%は貧困化するのである。そうして経済の無秩序化は深刻になっていく。グローバル化によって株価やGDPが上がったとしても、それは富裕層、大企業の懐に入るばかりで末端の庶民には行きわたらないのである。経済成長が即国民全員の豊かさとなる時代は終わったのだ。
続きを読む 【巻頭言】グローバリズム幻想を打破し、興亜の道を目指せ(『維新と興亜』第2号) →
道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)